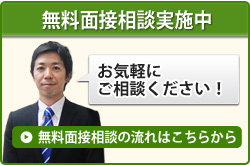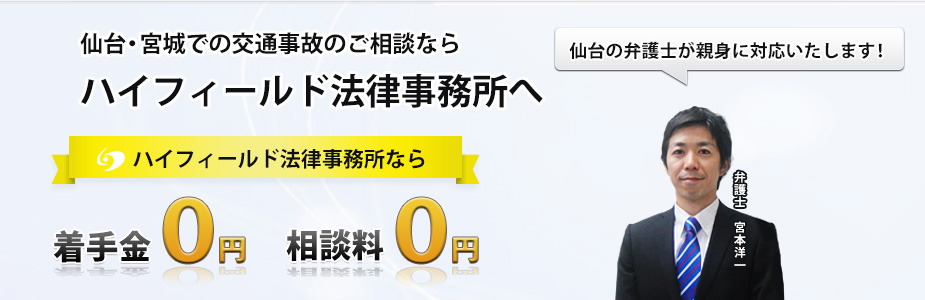
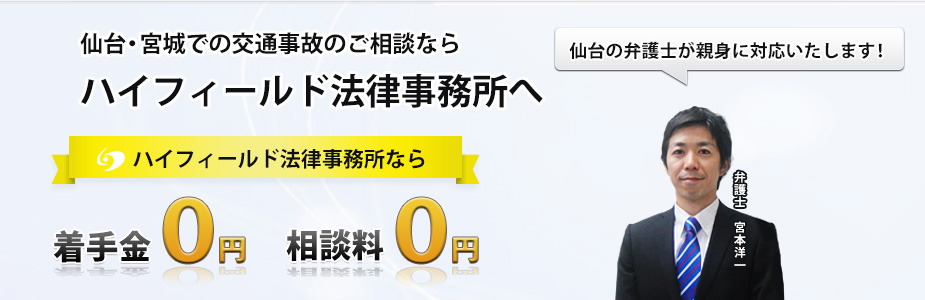
逸失利益について
逸失利益とは,本来得ることができたにもかかわらず,後遺障害によって得られなくなった収入相当額の損害をいいます。この場合の利益は,通常,所得収入になります。
そして,後遺障害による逸失利益は,基礎入額に,労働能力喪失率を乗じ,さらに労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数(中間利息控除係数)を乗じた金額で求めることができます。
労働能力喪失率について
労働能力喪失率については,裁判実務では,原則として,後遺障害の等級の程度に応じて,労働能力喪失率表に従い決定されます。
この喪失率表は,もともとは労働災害を補償する際の基準として定められた労働省労働基準局長通牒で示された基準を借用しているものです。
自賠責保険も労災の障害認定基準に準拠するとされていることから,同じ表を使って逸失利益の計算をすることになります。
| 等級 | 労働能力喪失率 | 等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|---|---|
| 要介護第1級 | 100% | 第7級 | 56% |
| 要介護第2級 | 100% | 第8級 | 45% |
| 第1級 | 100% | 第9級 | 35% |
| 第2級 | 100% | 第10級 | 27% |
| 第3級 | 100% | 第11級 | 20% |
| 第4級 | 92% | 第12級 | 14% |
| 第5級 | 79% | 第13級 | 9% |
| 第6級 | 67% | 第14級 | 5% |
このように,労働能力喪失率表を用いて,後遺障害の等級に応じた労働能力喪失率を客観的・形式的に決定することにより,裁判官ごとの判断のばらつきから生じる不公平感の発生を防ぐことができるという利点があります。
しかし,後遺障害による逸失利益は,「本来得られたであろう収入額と実際の収入額」の差額であることからすれば,労働能力喪失率に基づいて後遺障害による逸失利益が正確に導きだされるうるものではないはずです。
また,労働能力喪失率表を基準として労働能力喪失率を形式的に判断することで,かえって不公平感が生じることもあります。
そこで,裁判実務では,労働能力喪失率表に応じた労働能力喪失率を認めることを基本としつつ,事案に応じて,労働能力喪失率表から離れて労働能力喪失率を認めることがあります。
喪失率表とは異なる認定がされる場合
事故後に減収がない場合や喪失率に見合うだけの減収がない場合
逸失利益の概念からすれば,後遺障害を負っても実際に減収がない場合や喪失率に見合った減収がない場合には,そもそも損害が発生してない以上,逸失利益は認められないことになります。このような考え方を差額説と言います。
実際の減収がない場合,加害者側保険会社は,後遺障害遺失利益を認めないという対応をしてくるのが通常です。
この点について,最高裁昭和56年12月22日判決(民集35巻9号1350頁)は,後遺障害を負っても実際に減収がなかった事案で,「かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても,その後遺症の程度が比較的軽微であつて,しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては,特段の事情のない限り,労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。」と判断しています。
減収がなければ損害も発生していないともいえますが,逸失利益は将来の損害を予測して計算するもので,現時点で減収がないからといって,将来にわたって減収が発生しないとは必ずしも言い切れません。
上記最高裁判例も,このような実情を考慮して,差額説を基本としつつ,特段の事情がある場合には,例外を設けたものと考えられます。
そして,交通事故の後遺障害事案における裁判実務では,この最高裁判例が挙げた「特段の事情」を認定して,逸失利益を認めることが多い状況です。
事故後に減収がない場合や喪失率に見合うだけの減収がない場合の裁判では,①昇進・昇給等における不利益(将来の査定への影響),②業務への支障,③退職・転職の可能性,④勤務先の規模・存続可能性等,⑤本人の努力,⑥勤務先の配慮,⑦生活上の支障などから,「特段の事情」があるとして労働能力の喪失があることを主張立証していくことになります。
後遺障害の内容から喪失率表以上の労働能力の喪失を認めることができる場合(あるいは直ちに喪失率表どおりの労働能力の喪失を認めることができない場合)
労働能力喪失率表は,年齢・性別・職業等の違いを考慮することなく,後遺障害の等級(後遺障害の内容・程度)のみに着目して,労働能力喪失率を客観的・形式的に判断しています。
しかし,事案によっては,年齢・性別・職業等の違いを考慮しないで労働能力喪失率を決定ことで,かえって不公平な結果を招く場合があることは否定できません。
例えば,事故により人差し指一本を切断した場合をみても,被害者の職業がピアニストかサッカー選手かで労働能力に及ぼす影響は全く異なることは,想像に難くないでしょう。
札幌地判平成27年2月27日(自保ジャーナル1945号)も,「不法行為による損害賠償は,当該被害者に具体的に生じた不利益を補てんして,不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであるから,当該被害者の上記の職業能力的諸条件を具体的に検討した上で労働能力喪失を判断する必要がある。その検討の結果として,自賠責保険の後遺障害の一般的な労働能力喪失率と一致する場合も多いであろうが,この一般的な労働能力喪失率を形式的,画一的に適用すべきものではない。」と判示しています。
交通事故の後遺障害事案における裁判でも,労働能力喪失率表にとらわれないで労働能力喪失率を認定しているものが多数あります。
裁判で,このように労働能力喪失率表から離れた労働能力の喪失を主張する場合には,①後遺障害の内容・程度,②職業・労働能力の内容,③事故後の勤務状況・稼働率,④退職の有無,⑥事故前後の収入前後の差,⑦日常生活での支障,⑧就労の可能性,⑨年齢,⑩職歴などから,具体的な労働能力の喪失を主張・立証することになります。
後遺障害を理由に,勤務先を退職せざるを得なくなったような事情がある場合には,労働能力喪失率表に応じた以上の労働能力の喪失が認められる余地が大きいものといえます。
逆に,障害の内容によって,喪失率表どおりの労働能力の喪失が認められない場合もあります。
例えば,外貌醜状の後遺障害で,被害者が女性で等級が低い場合(12級)には,逸失利益を否定するものがやや多いです(もっとも,この場合でも後遺症慰謝料を基準より増額認定するものがあります)。これも,被害者の障害内容,年齢,職業などに照らし,労働能力喪失率表に対応するほどの労働能力が失われていない状態が継続すると判断されるかどうかによるでしょう。
労働能力喪失期間について
後遺障害は,生涯残るという前提で等級が認定されるものであるため,労働能力喪失期間は,就労可能とされる年齢までの分が認められるのが原則です。 実務上,就労可能とされる年齢は67歳とされています。これは昔の簡易生命表から導き出された数字です。既に67歳を超えている者や, 症状固定日から67歳までの年数が簡易生命表による平均余命の二分の一より短くなる者の場合は,平均余命の二分の一の期間を喪失期間とします。
ただし,後遺障害の種類や被害者の年齢などにより,必ずしも同程度の労働能力の喪失が生涯続くとは 言い切れないケースも存在します。例えば,むちうちの場合などには,痛みは慣れたり将来的に軽減することがあるからといったことや代替動作を獲得するといったことを理由に,労働能力を喪失する期間を限定されることがあります。
14級の場合で3~5年程度,12級の場合でも10年程度で喪失期間は打ち切られています。
ただこれもあくまでも目安で,事案によっては,14級の場合でも10年以上の喪失期間が認められているものも多数あります。
自分が負った後遺障害を理由に,どの程度の逸失利益が生じているのかを詳しく知りたいかたは,一度専門家に相談してみるのがいいでしょう。